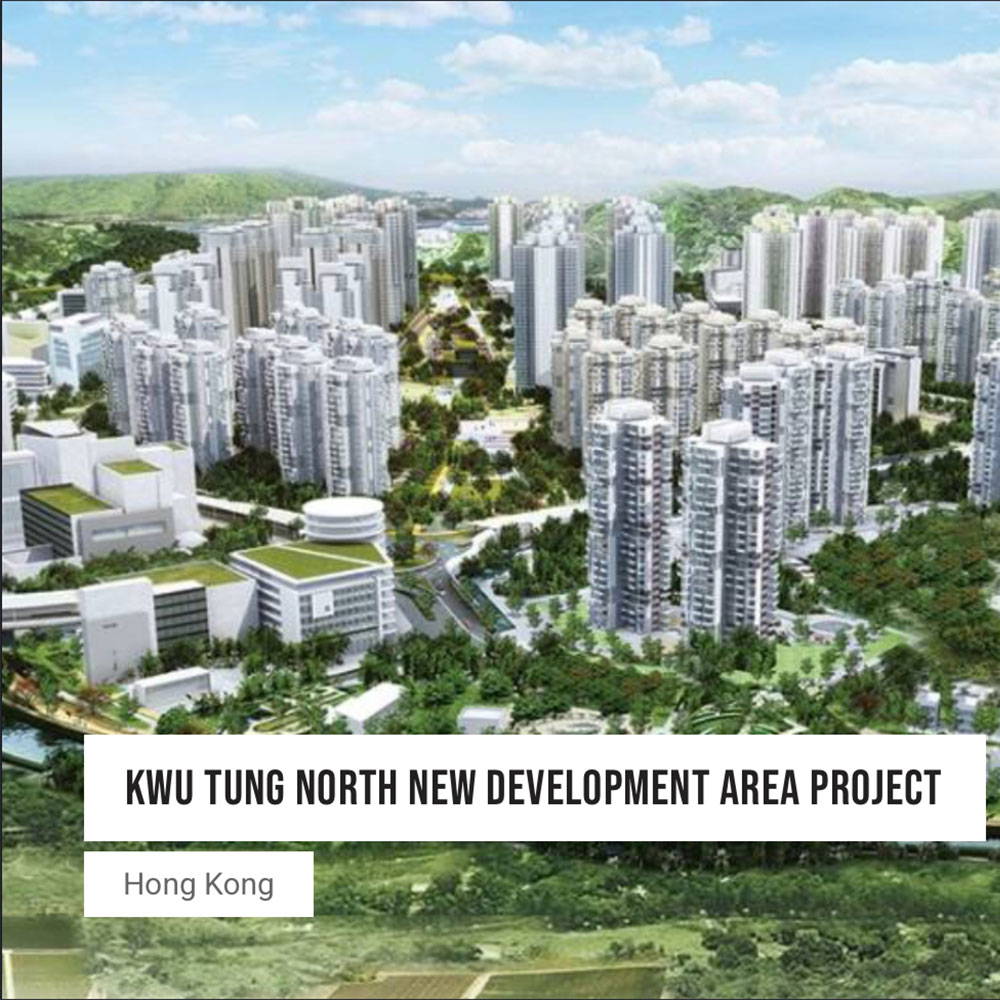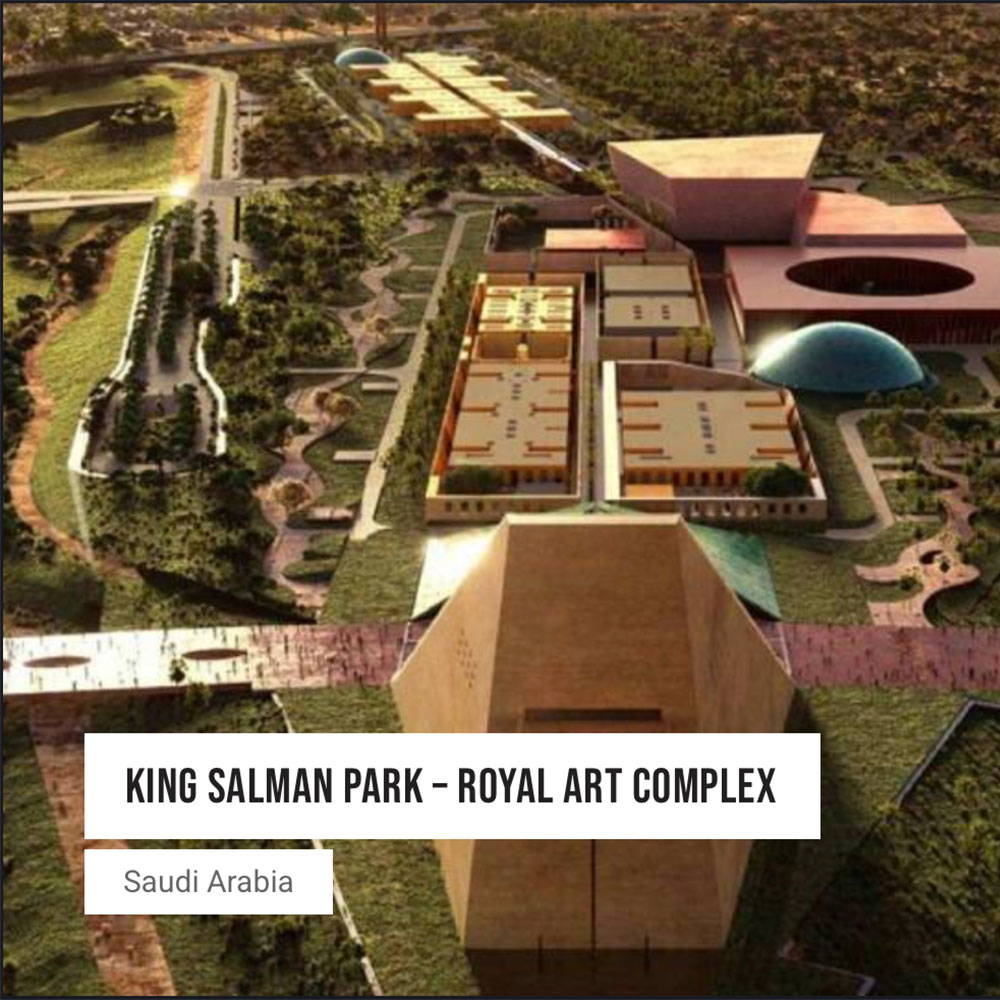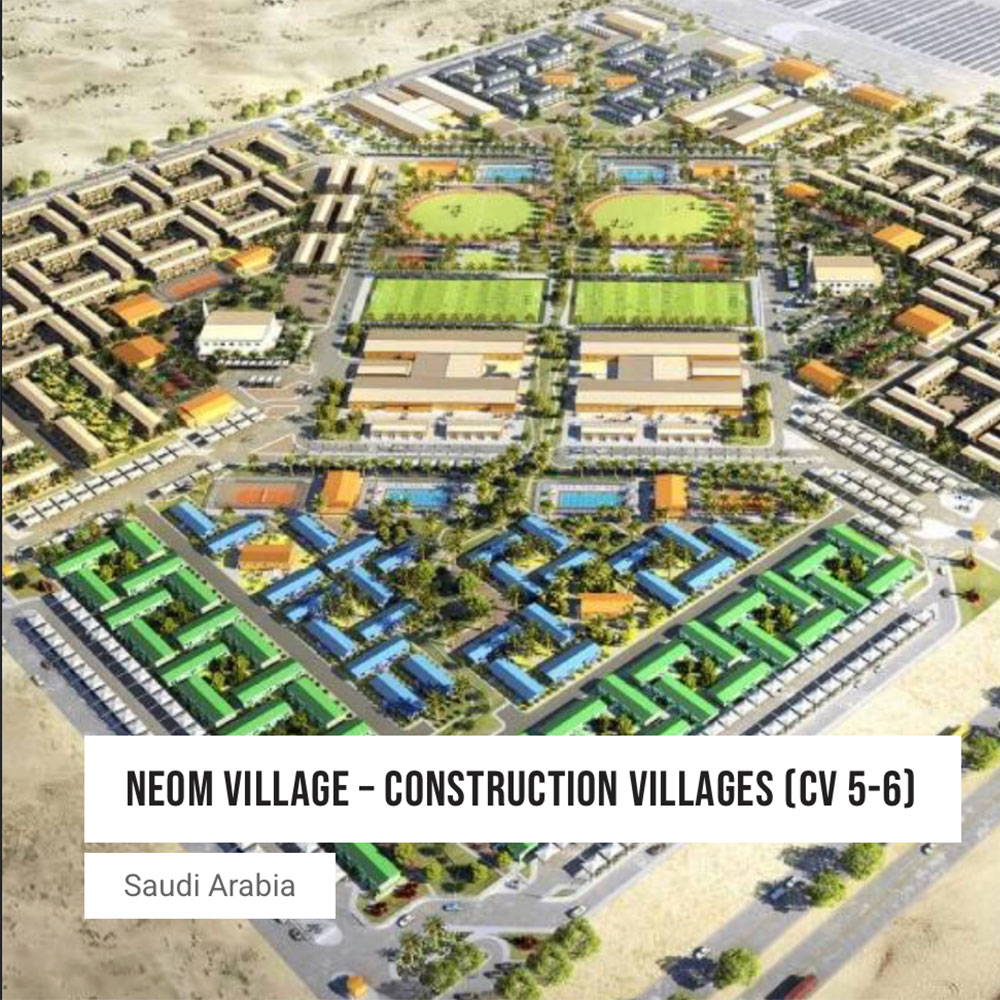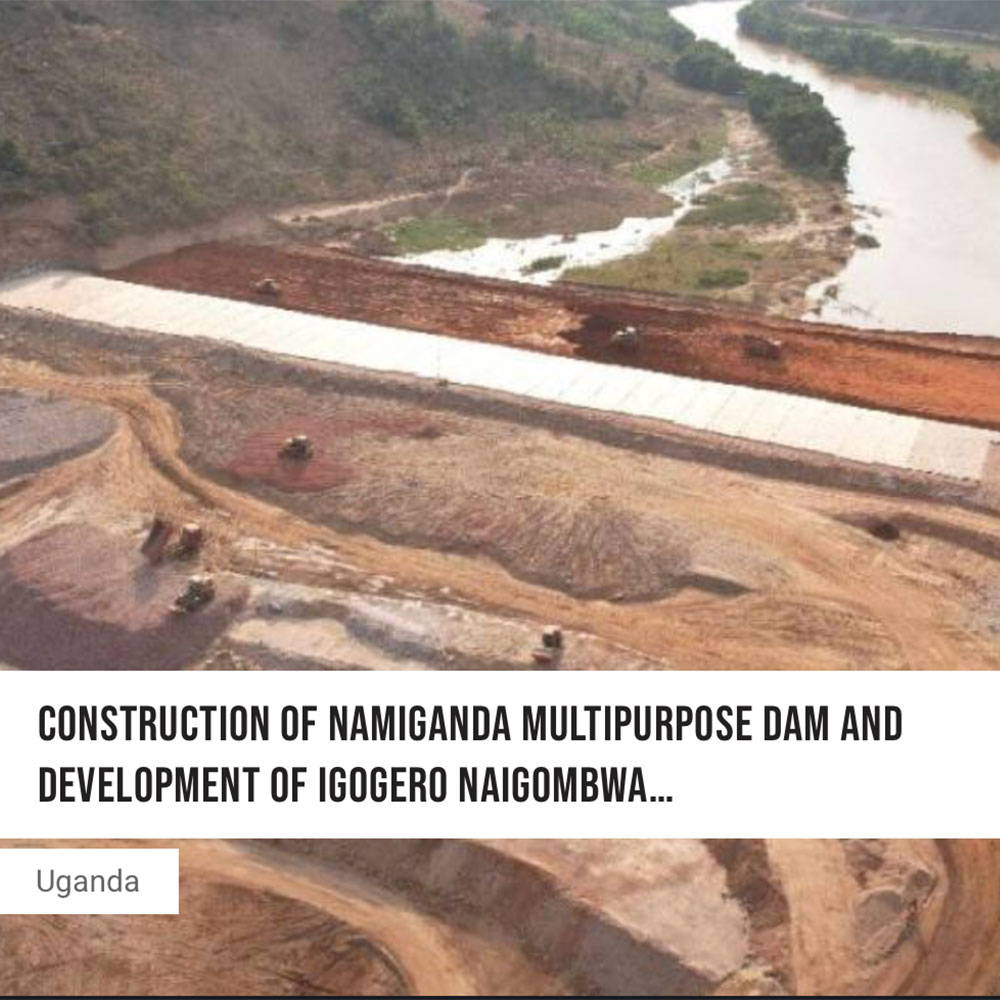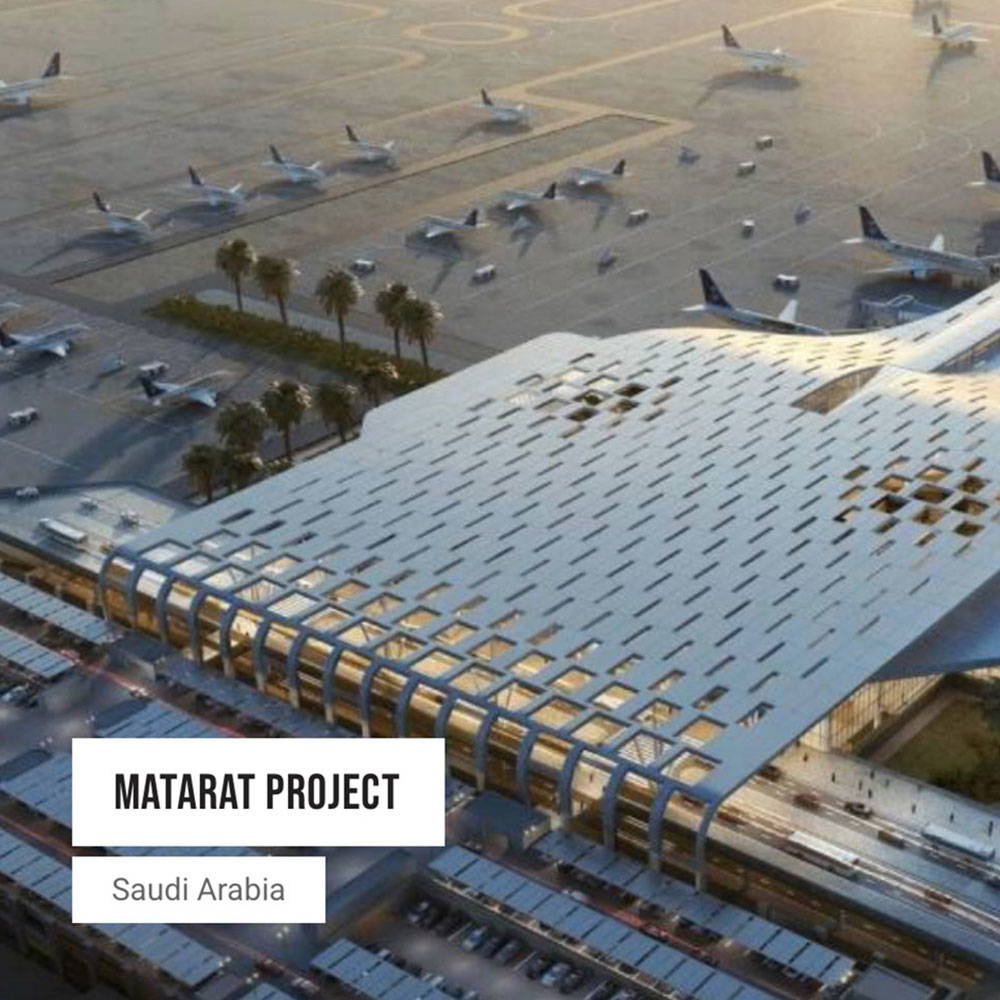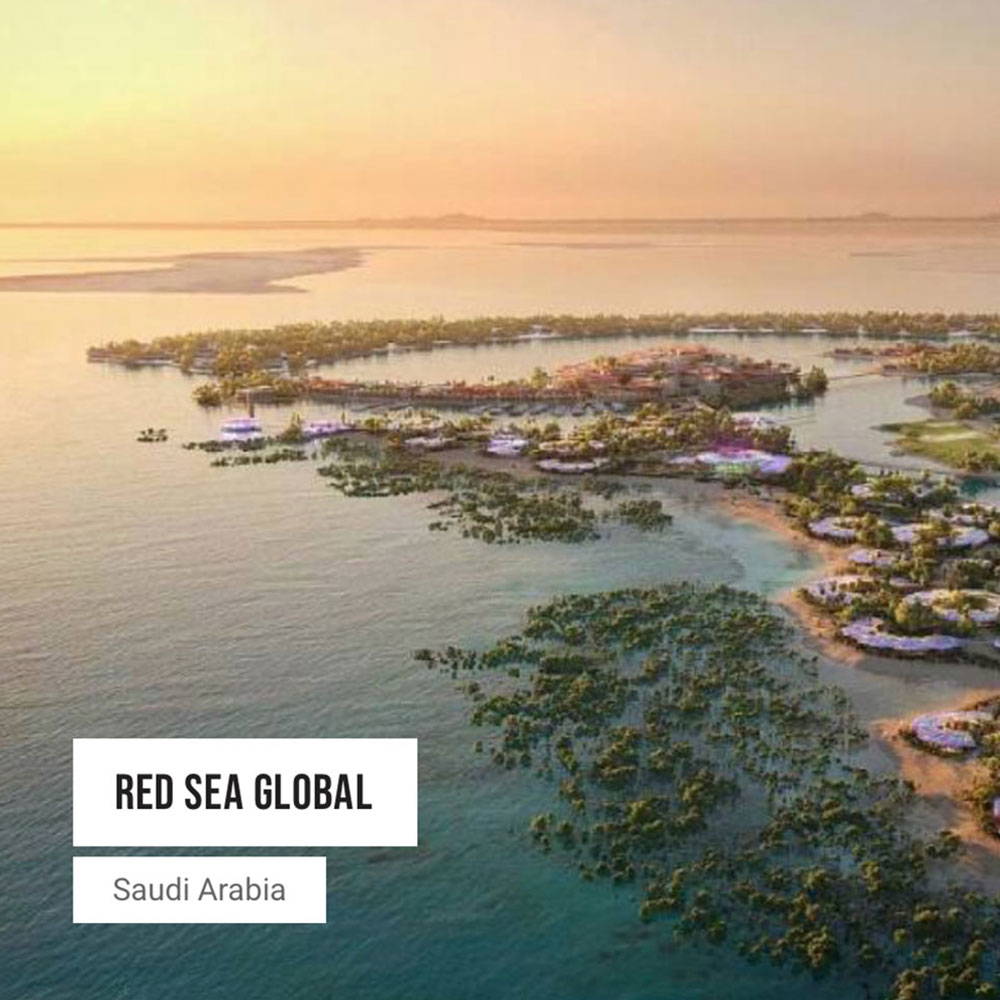従業員自身または従業員に代わって発生する旅費や宿泊費は、多くの問題を引き起こします。
旅行や生活費に対する税控除が受けられるかどうかを判断する際に考慮すべき主な点を以下に説明します。
常勤の従業員
多くの従業員は定期的に出勤する職場があり、時折、通常の職場から臨時の職場へ出勤します。自宅から臨時の職場へ直接出勤したり、その逆を行ったりする従業員も少なくありません。
従業員は、出張にかかる税金の全額控除を請求できます。
ビジネス旅行
出張とは、次のいずれかの旅行を伴うものです。
- 職場から職場へ、あるいは
- 自宅から一時的な職場へ、または
- 臨時勤務先から自宅へ。
従業員の自宅と定期的に通う勤務地との間の移動は、出張とはみなされません。これらの移動は「通常の通勤」であり、その費用は従業員が負担する必要があります。「常勤勤務地」とは、従業員が「定期的に」通う場所と定義されます。これは、通常の通勤における移動の一方の終点を定めるために使用されます。通常の通勤におけるもう一方の終点は、自宅です。
例1
従業員は通常、ヨークの自宅とリーズの通常の勤務地の間を車で通勤しています。これは毎日往復48マイル(約72キロメートル)です。
ある日、従業員はヨークの自宅からノッティンガムの臨時勤務地まで車で移動しました。往復174マイル(約270キロメートル)です。
ここでの費用は、実際に行った旅行の費用(174マイル)です。この金額は控除の対象となります。
例2
普段は北へ40マイル(約64キロメートル)運転して通勤する従業員が、顧客の敷地まで南へ100マイル(約160キロメートル)往復する必要がありました。雇用主は、この100マイルの通勤費用を従業員に払い戻しました。
その金額については控除を受けることができます。
生活費の支払い
滞在費には、従業員が常勤の勤務地を離れている間の宿泊費、飲食費が含まれます。滞在費は出張に伴う費用として扱われるため、出張費の一部として扱われます。
反回避
一時的な職場と自宅の間の移動は、その移動が常勤の職場への往復の移動と「実質的に同様」である場合、減免の対象とならないことがあります。
HMRC では、「実質的に同様」とは、旅程の大部分で同じ道路、同じ電車、またはバスを使用する旅行であると解釈しています。
臨時雇用
従業員が何ヶ月もの間常勤の職場を離れる場合、新しい職場は、その配置が次のいずれかに該当する場合には臨時の職場とみなされます。
- 24ヶ月未満と予想される、または
- 24 か月を超えると予想される場合、従業員は新しい職場で労働時間の 40% 未満を過ごすことが予想されます。
従業員は引き続き恒久的な勤務地を維持しなければなりません。
例3
エドワードはニューブライトンで働いています。雇用主は彼を28ヶ月間、週1.5日、レクサムに派遣しています。
エドワードは救済措置を受ける権利があります。40%ルールに違反しない限り、24ヶ月を超える駐在期間も引き続き対象となります。
現場従業員
従業員の中には、通常の勤務場所を持たず、数日、数週間、または数ヶ月にわたって複数の場所で勤務する人もいます。現場勤務の従業員の例としては、建設作業員、安全検査員、コンピューターコンサルタント、救援活動員などが挙げられます。
現場従業員の旅費および滞在費は、現場での滞在期間が 2 年未満と予想され、実際に 2 年未満である場合は、非課税で払い戻すことができます。
減免措置が適用される場合、雇用が真に現場ベースであることを保証するための租税回避防止規定が設けられています。例えば、臨時雇用の場合、雇用期間の全部またはほぼ全部において当該職場で職務が遂行されるときは、減免措置の適用から除外されることがあります。これは特に、24ヶ月の制限を不当に操作して、反復的な臨時雇用を行うことを防ぐことを目的としています。
常勤勤務先のないその他の従業員
出張予定
従業員の中には、出張が業務の不可欠な一部となっている人もいます。例えば、勤務地や定期的な出勤場所を持たない巡回セールスマンなどが挙げられます。このような従業員が負担した旅費および滞在費は控除の対象となります。
在宅勤務者
従業員の中には、時折、あるいは定期的に自宅で仕事をする人もいます。これは必ずしも自宅を勤務場所とみなせるという意味ではありません。業務が他の場所ではなく自宅で行われるという客観的な要件が必要です。
これは、従業員が「定期的に出勤する」オフィスなど、別の場所が恒久的な職場となることを意味する場合があります。したがって、自宅とオフィス間の通勤費は経費として認められません。ただし、自宅と臨時の職場間の移動費は経費として認められます。
恒久的な職場がない場合、従業員は現場勤務者として扱われます。したがって、雇用主のオフィスへの出張費用も含め、すべての費用が認められます。
上記の客観的な基準に基づき、自宅は依然として職場とみなされる場合があります。その場合、同一の雇用に関する自宅と他の職場間の移動は認められます。